新2号の構造関係規定について(調整中)
新2号の構造関係規定について
Pは、改正建築基準法 2階建ての木造一戸建て住宅(軸組構法)等の
確認申請・審査マニュアルのページ数に対応
1. 前提条件P78
- ●階数が2以下
●高さ16m以下
●木造軸組工法
●基礎が鉄筋コンクリート
●延べ面積が300㎡以下
●階高が3.5m以下
●平面形状や断面形状が著しく特殊でないもの
●構造計算を行わず、仕様規定のみで構造安全性の確認を行うもの
2. 壁量の確保 P82
| A.早見表 P83 | B.表計算ツール P84 | C.地震力の算定 建物荷重の算定→地震力→必要壁量の算定 ※許容応力度と同じ |
| 存在壁量≧必要壁量 | ||
| ※問題点 構造設計者が耐力壁の配置を計画、梁伏は設計をせず、プレカットが梁伏を行う場合 耐力壁内に梁継ぎ手、耐力壁の端部に梁段差→耐力壁にならない箇所が出る 2階の梁上に載る耐力壁の低減計算が出来ない→耐力壁が不足する場合あり |
||
3.壁配置バランス(四分割法) P96
※偏心率でも可能だが、簡易な計算で求めた偏芯率と許容応力度計算で求めた偏心率は
大きく異なる場合あり
(重心の違い 簡易な計算は図芯=重心 許容応力度計算は重心(荷重の中心))
問題点
四分割法を満たしても、許容応力度計算では偏心率0.15以上でねじれ補正が生じ
計算を満たさない場合あり
4.柱頭・柱脚の接合方法 P100
| N値計算法 | 告示 (平12建告第1460号第2号イ)の仕様 |
| ※従来の計算手法にない高さでの割り増しあり 横架材間距離3.2m超は割り増し計算 |
※階高3.2m以下 |
| ※問題点 構造設計者が耐力壁の配置を計画、梁伏は設計をせず、プレカットが梁伏を行う場合 梁伏により、2階の柱→1階の柱のN値の伝達が異なる 構造設計者が柱頭・柱脚の金物の納まりの検討できない |
|
5.柱の小径等 P108
(1)柱の小径 P108
| A.早見表 | B.表計算ツール |
| ※PH階、小屋裏収納は対象外 | ※PH階、小屋裏収納は対象外 |
|
追加検討(上記の計算NGで柱の小径を大きく出来ない場合) |
(2)柱の有効細長比 P112
※問題点
構造設計者が耐力壁の配置を計画、梁伏は設計をせず、プレカットが梁伏を行う場合
耐風梁・耐風柱の設計が出来ない(耐風梁の検討には火打ち位置も影響します)
6.その他のチェック P115
(1)基礎の仕様 P115
地耐力に応じた基礎構造 P117
令第38条、平12建告第1347号より決定
問題点
PH階、小屋裏収納、インナーガレージは対応にしていないのでは?
許容応力度計算をすると、満たさないケースが多々ある
地盤改良にも影響する
地盤沈下の可能性あり
許容応力度計算の地耐力の算定
長期設計地耐力=(建物重量+基礎重量(基礎伏・基礎断面が必要))/べた基礎面積
長期設計地耐力は簡易に算定不可
基礎の仕様 [平12建告第1347号] P119
問題点
この仕様を守れば計算上NGでも良いのか?
地中梁部等についての記載なし 構造計算を行うのか?
鉄筋の継手、定着についての記載なし
RC規定を順守するのか?
P119にスターラップ(せん断補強筋)はフック付き、もしくはユニット鉄筋を用いる必要ありと記載
P118人通口まわりの補強例5)柱間隔が1.82mを超える場合は、構造計算を行い適切な補強を行う
この構造計算をする場合、長期設計地耐力の算定と同じ手順の計算を行う必要があり簡易には出来ません
その他
P66
申請図書 基礎の仕様(一般部の基礎断面及びスラブ配筋、人通口の開口部補強)
A.Bルートでは一般的には梁せいと基礎断面の決定には
「木造軸組工法住宅の横架材及び基礎のスパン表(2018年版)」を用い設計しますが、
2018年版はZEH住宅の重量には非対応で使えないです。
(確認検査機関も通させないと言っています)
(品確法の壁量計算ルートも、この本も用い設計しますが、新版が出ない為、梁せい、
基礎について計算が行えず、業務が止まっている事務所があり、
許容応力度計算での申請に切り替えを検討しているそうです)
基礎のみ許容応力度計算するには建物重量、基礎重量(基礎伏・基礎断面が必要)の算定が
必要になります。
上記の算定をするなら、許容応力度をした方がいいです
※なんの根拠もなしに申請だけ通すなら計算は不要ですが、伏図は保存図書ですので根拠がないと設計者責任が問われます。
地中梁、人通口で柱間隔が1.82mを超える場合は質疑の可能性あり(許容応力度計算で対応になる可能性あり)
補足
「木造軸組工法住宅の横架材及び基礎のスパン表(2018年版)」は、適用条件が厳しくほとんどの物件で適用出来ない為に、
これより古い書籍「木造住宅の為に構造の安定に関する基準に基づく横架材及び基礎のスパン表」を悪用している設計者が多数います。
古い書籍は無効という一筆がない為に法的には有効だとのことです(4号廃止前は)。
古い書籍の想定する建物荷重が軽く鉄筋量が許容応力度計算より減らせます。
その荷重でスパン表に記載のない地中梁を設計して方がいます。(品確法の壁量計算ルートで申請している設計者 大手ハウスメーカーでも見かけます)
検査機関はZEH基準になり建物が明らかに重くなる為に認めない方針だそうです。
どの検査機関に問い合わせてもZEH基準の新しいスパン表が発行されるという情報はありません。
とりあえず、基礎の計算は建物荷重と基礎荷重を求めて許容応力度で設計する方が無難です。
新2号で簡易な計算(A.早見表もしくはB.表計算ツール)で対応出来ない物件
(許容応力度でしか対応出来ない物件)
・前提条件 P78に適合しない物件
・特殊な形状 平面・立面不整系(コの字、オーバーハング等)
・吹抜けあり(耐風梁の検討不可 大きな階段室も吹抜け扱いになるので注意)
・表計算ツールの解説・注意事項に記載の荷重・条件以上の仕様
(ある程度は安全側の設計にし対応は可能 安全側の設計になるかは検証が必須)
・PH階、小屋裏収納あり、その他特殊な荷重あり
・B.表計算ツールで柱の小径がNGで追加検討を要する場合
・地中梁等の立上りがない基礎がある場合
・人通口で柱間隔が1.82mを超える場合
※簡易な計算で申請の場合は、構造設計者として名義は張れません
※伏図はプレカットが設計しますので、当方で行う設計とは整合は取れません
基本的には許容応力度設計をお勧めします。
簡易な計算は構造設計者として安全性は担保出来ないと考えます。
そして、伏図をプレカットが設計しますので、整合が取れません。
耐力壁の認定等を厳密化するという話もあり、プレカットでは対応出来ないと思います。
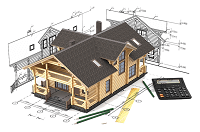
ダイガク二級建築士事務所
二級建築士事務所埼玉県知事登録
第(2)11349号
二級建築士茨城県知事登録
第12317号
大槻 学
〒336-0911
埼玉県さいたま市緑区三室694-9
TEL.090-8309-3531
info@daigaku.biz